きび団子専用の執事、かしわ餅に、急遽用意された部屋に通されたあずきは、目の前で唸っているきび団子を見た。
カステラのベッドに、八つ橋で出来た布団の上に転がっている黄土色の菓子団子は、頭に乗せている王冠を器用にくるくる回している。
どうやらきび団子なりに思案しているようだ。
「あの、あたし」
その真剣な面持ちのきび団子に、あずきは恐る恐る話し掛けた。
だが、きび団子は、あずきの顔をちらりと見て、「こんなにも素敵な人なのに」と小さく呟き、溜息を吐いた。
余りに真剣に考えている為、あずきの呼び掛けを気に止める素振りは見せない。
寧ろ、常にマイペースなきび団子は、基本的には自分の事しか考えていなかった。
きび団子の父である王、饅頭に反対されたこのきび団子は、とても困っていた。
きび団子にとって、愛する女性はあずきのみ。
生まれてこの方、あずき以外の女を女として見た事もない。
云わば、これが初恋でもあるのだ。
きび団子は、この城の長男だ。
弟にチョコレートきび団子とマスカットきび団子が居るには居るが、本来であれば、将来この城を継ぐのは、長男であるきび団子だろう。
その為には、父のように、お后を娶らなければならない。
だが、父は、そのお后に人間であるあずきは受け入れないと言う。
どうしたものかと、きび団子は考えた。
八つ橋の布団の上で、時折ごろごろと転がって考えてみた。
その横で、あずきも黙って八つ橋の布団の上に腰掛け、これからどうするべきかと考えていた。
あずきは、こんな所に、嫁になる為に来た訳ではない。
己は、弟の栗太郎の為、シュークリームを買おうとしていだけなのだ。
それが、ひょんな事に巻き込まれ、今では和菓子の国の王子様と一緒に居る。
どうすれば帰る事が出来るだろうかと、あずきは「うーん」と頭を捻った。
その横で、きび団子も、どうすれば父に認められるだろうと、相変わらず頭を悩ませていた。
いっそ駆け落ちでもしてやろうかと思ったが、この狭い和菓子国で逃げ切れるだなんて有り得ない。
隣国の洋菓子国にでも行けばどうにかなるかもしれないが、それは和菓子としてのプライドも許さなかった。
二人が居るのは、今日はもう遅いので此処に泊まれば良いと通された、和菓子だらけの部屋。
その部屋は、きび団子が普段使っている私室の隣だった。
和菓子達の身体は非常に小さいが、何とかあずきが寝転ぶだけの大きさを持ったカステラのベッドが中央に置かれていた。
カステラは、まるでウォーターベッドのように弾力がいい。
その上に敷かれた、ふかふかの八つ橋布団。
もなかで出来たローチェスト、ドレッサー。
其処は、ヘンゼルとグレーテルの日本版の世界にでも来たような空間だった。
和菓子が大好きなあずきからすれば、そのどれもが魅力的に映った。
出来れば永住して、思う存分此処の和菓子を食べ尽くしたかった。
だが、あずきは帰らなければならなかった。
好きだと言ってくれたきび団子には申し訳ないが、あずきはまだ年端もいかぬ十四歳で、家業を手伝わなければならない身でもある。
そもそも、お菓子の嫁になどなれる筈がない。
あずきは、未だ唸っているきび団子に目を遣って、今夜、皆が寝静まったら、この城から出て行こうと考えた。
きび団子の想いを後ろ足で蹴るような遣り方だが、話を聞いてくれない相手では、それも致し方なかった。
窓の外を見れば、空もとっぷりと暮れていた。
今頃、家では家族が心配しているだろう。
夜通し捜索されるかもしれない。
あずきの心が、ちくんと痛んだ。
「なぁ、もう寝よう。
明日考えるようにすればええが」
あずきは、益々家に帰りたくなり、一緒に居るきび団子を急かすように言った。
きび団子をさっさとこの部屋から追い出して、私室に戻らせ、己は家に帰る準備をしなければならない。
このきび団子が居なくならない限りには、城を出て行くどころか、この部屋すらも出て行けない。
「ん?
もうあずきは眠いの?」
そのあずきの催促に、やっとまともな反応をしてくれたきび団子は、きょとんとしてあずきを見た。
空はもう真っ暗だが、寝る時間にしては少々早いらしい。
けれど、そんな事を気にしていられないあずきは、「うん」と首を縦に振った。
「そうか、じゃあ電気を消そうね」
きび団子は、ぽんぽんと弾んで電気を消しに行ってくれた。
あずきは、八つ橋の布団の中に潜り、ほっと溜息を吐いた。
これできび団子の監視は免れる。
城を抜け出す第一歩にもなる。
だが、事はそうも簡単にいかなかった。
ふと横を見れば、再び戻って来たきび団子が、当たり前のように横になっている。
球形をしているので、果たして横になっているのかどうかは怪しいが、だが明らかに寛いでいるようではあった。
どうやら、きび団子も此処であずきと一緒に眠るつもりらしい。
あずきは慌てて半身を起こした。
「ちょ、ちょっと!」
「何?
眠れなかった?」
「そ、そうじゃなくて!
いや、そうじゃけども」
「ああ、そうか。
僕達はもうフィアンセなんだから、おやすみのキスが要るんだね」
どもって声を荒げたあずきに、きび団子はあっけらかんとして言いのけた。
余りに頓珍漢な答えが返って来た事にあずきは驚いて、ぽかんとしてしまった。
その隙を突いて、きび団子はぽんと跳ね上がり、あずきの口元まで飛んできた。
ほんの一瞬ではあるが、あずきの唇に、きび団子のもちもちした生地が触れた。
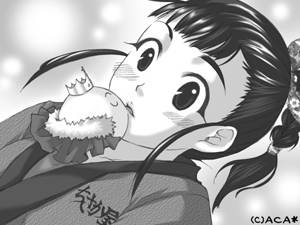
相手は、ただのきび団子である。
普段、毎日食しているきび団子である。
だが、今まで一度もキスなどした事がなかったあずきは、思い切り顔を赤くし、今度は違う意味で硬直した。
あずき程の年になれば、ファーストキスはレモンの味だの何だのと、友達同士で盛り上がる事もある。
しかし、あずきのファーストキスは、いつも味わっている筈のきび団子の味がした。
「ギャー!」
ワンテンポ遅れて叫んだあずきは、顔を八つ橋に埋めて大騒ぎした。
こんな事になるだなんて、思ってもみなかった。
これでも一応、あずきも夢見る乙女である。
ファーストキスは、目が眩むような格好いい年上の男性と、とろけてしまうようなシチュエーションでするのだと信じていた。
白馬の王子様よろしく、素敵な男性に愛されて、お姫様のような一時になるのだと思っていた。
それなのに、まさか相手がきび団子だなんて。
一応王子ではあるが、人間ですらない、丸いお菓子だなんて。
あずきは、恥ずかしいやら泣きそうやらで、もう一度大きな声で叫んだ。
だが、これにはきび団子が吃驚した。
当たり前のようにした就寝の挨拶が、こんなにも驚かれるとは思わなかったのだ。
父には認められていないが、紛いなりにもフィアンセになったのだから、これくらいは当然だと思っていた。
それなのに、あずきは想像していた可愛らしい反応など全く見せず、寧ろ大いに嫌がっているようにも見えるのだ。
「あずき、どうしたんだい?」
八つ橋の布団の中で蓑虫になってしまったあずきに、きび団子は優しく話し掛けた。
しかし、あずきは小さくうめくだけで、きび団子の声には応じない。
何度呼び掛けても、一向に返事すらしない。
おかきの時計がボーンと音をたてて、もう九時になったと知らせてくれた。
参ってしまったきび団子は、どうしたのだと問うのを止めて、今度は「御免よ」と謝った。
何が悪いのかなどとんと分からなかったが、とりあえず謝ってみた。
しかし、それが功を奏したのか、その謝罪の言葉に、あずきはぴくりと肩を震わせた。
あずきは、きび団子に対して怒っている訳ではなかったのだ。
ただ、ファーストキスがレモンの味ではなかったとか、相手が年上の男性ではなかっただとか、この夢の無い展開にショックを受けていただけだったのだ。
それなのに、何やらきび団子を困らせ、謝らせてしまったようだ。
八つ橋から顔を出した人の良いあずきは、やや疲弊したきび団子を見た。
きび団子は、眉毛を八の字にして笑っていた。
黄土色の生地に、ちょこんと乗った王冠、小さなマント。
何処からどう見ても、ただ顔があり、ものを喋る、一寸おかしな和菓子である。
そうだ、相手はただのきび団子なのだ。
きび団子なら、毎日飽きるほど食べている。
そんな物が唇に当たったからとはいえ、それがキスになる訳がない。
小さな子供同士がふざけてキスしたのと同等レベルだ。
そう思えば、動転していた心も些か納得した。
「あずき、落ち着いた?」
「うん」
「そう、それは良かった。
じゃあ、今度こそ眠ろうね」
あずきが機嫌を直したと悟ったきび団子は、ほっとして笑った。
急に失礼な態度を取った事には怒らず、ただあずきが顔を出してくれた事に喜んでいるようだ。
とはいえ、実際、突然突飛な事をしでかしたのはきび団子の方なのだ。
それなのに、やはり気の優しいあずきは、逆に申し訳なさを感じていた。
きび団子には、悪気がなかったのだ。
それなのに、矢庭に叫んだりして、小さな幼子が拗ねるような真似までしてしまった。
そう思うと、自分の方こそが悪いような気がしてきた。
あずきは、小さなきび団子を、何処か母性にも似た感覚で見ていた。
そのせいで、己の方こそが大人気無いと感じてしまった。
もぞもぞと同じ布団に包まれて、再度天井を見詰めてみる。
人間ときび団子というその組み合わせは、余りに滑稽で不似合いだ。
「なあ、きび王子」
首を横に傾けて、あずきは言った。
きび団子は、あずきに話し掛けられた事が嬉しいのか、にこにこして「何?」と返す。
「さっき、御免な」
「何であずきが謝るの?」
「そ、それは」
「あずきはいけない事をしたの?」
「そういう訳じゃねぇと思うけど」
「じゃあ、何?」
丸い和菓子は、然して気にしている素振りも見せず、相変わらずそれなりにご機嫌なようだった。
あずきは、もごもごと口を動かしながら下を向く。
「は、初めてじゃったから」
「初めて?
何が?」
「は、初めてチュウしたから、ちょ、ちょっとビックリして」
「へえ?」
「で、でも、相手は人間じゃないから、だ、大丈夫というか、何というか」
八つ橋布団を目の高さまで上げて、あずきは聞こえるか聞こえないか微妙な大きさで言った。
だが、それを言ったと同時、目の前は真っ白な煙に包まれた。
きび団子の姿も見えなくなった。
しかし、そのきび団子の姿を探す前に、ぐっと身体を引き寄せられて、八つ橋布団も剥ぎ取られ、また唇にきび団子の味がした。
何が起こったのか分からなかったあずきは、抵抗の暇も無かった。
煙幕が薄くなれば、やっと目の前が明らかになり、現状を知る事が出来た。
だが、あずきの目の前には、随分とドアップで端整な人間の男が映っている。
見た事はある。
きび団子の人間用の姿だ。
何がどうなっているのかと考える間もなく、口の中にどろりとした固体が捻じ込まれ、そこからまたきび団子の味がした。
味こそ美味いが、その初めて捻じ込まれたぬるぬるした固体は、とても気持ちが悪かった。
その固体は、あずきの意思などお構いないに口内を蹂躙し、あずきの舌まで絡め取ってきた。
執拗に動くそれに為す術もないあずきは、ぎゅっと目を瞑って耐えるしかなかった。
だが、そのぬめぬめした固体は、優しくあずきの心すらも掬っていった。
気持ち悪い筈が、身を任せている内、次第に蕩けるような心地になった。
男の確りした腕で強く抱き締められ、鼻の中一杯に広がるきび団子の匂い、口一杯に拡がるきび団子の味。
若干十四歳のあずきは、その官能的な行為に、みるみる落ちていってしまった。
数十秒、或いは数分もしてから、やっとあずきの口は解放された。
ゆっくりと目を開ければ、今日、全裸をお見舞いしてくれたきび団子の人間の姿が変わらず其処にあった。
だが、今では先の失態を反省に、きちんと白のシャツを着ているようだ。
とろんとした目で見詰めれば、きび団子の王子はにこりと笑う。
あずきは、これが本当のキスというものだろうかと、その腕の中に抱かれたまま、本格的に目を閉じてしまった。
ドキドキは止まらなかったが、不思議と心地良い眠りがあずきを襲った。
柔かい温もりと大好きな香りに包まれて、乳飲み子に戻った気すらした。
だが、快い気分に浸っているあずきとは裏腹に、少し気を抜いてしまったきび団子は、甚く焦っていた。
きび団子は、人間の姿になろうと思えば、いつでもなれる。
しかし、ほんの少しでも気を抜いた瞬間に、その姿は元のきび団子に戻ってしまうのだ。
あずきと共に眠ってしまったきび団子の王子は、気が付けば人間の姿から、元の球体に戻っていた。
その為、深い眠りに入ったあずきにむんずと掴まれ、事も有ろうか食われそうになったのだ。
間一髪のところで逃れる事は出来たものの、この日、きび団子は生まれて初めて命の危険を知った。
それ以来、「あずきが眠っている所では、何が何でも人間の姿を死守しなければ」と心に誓うきび団子が居たとか、居なかったとか。
TO BE CONTINUED.
2008.08.26